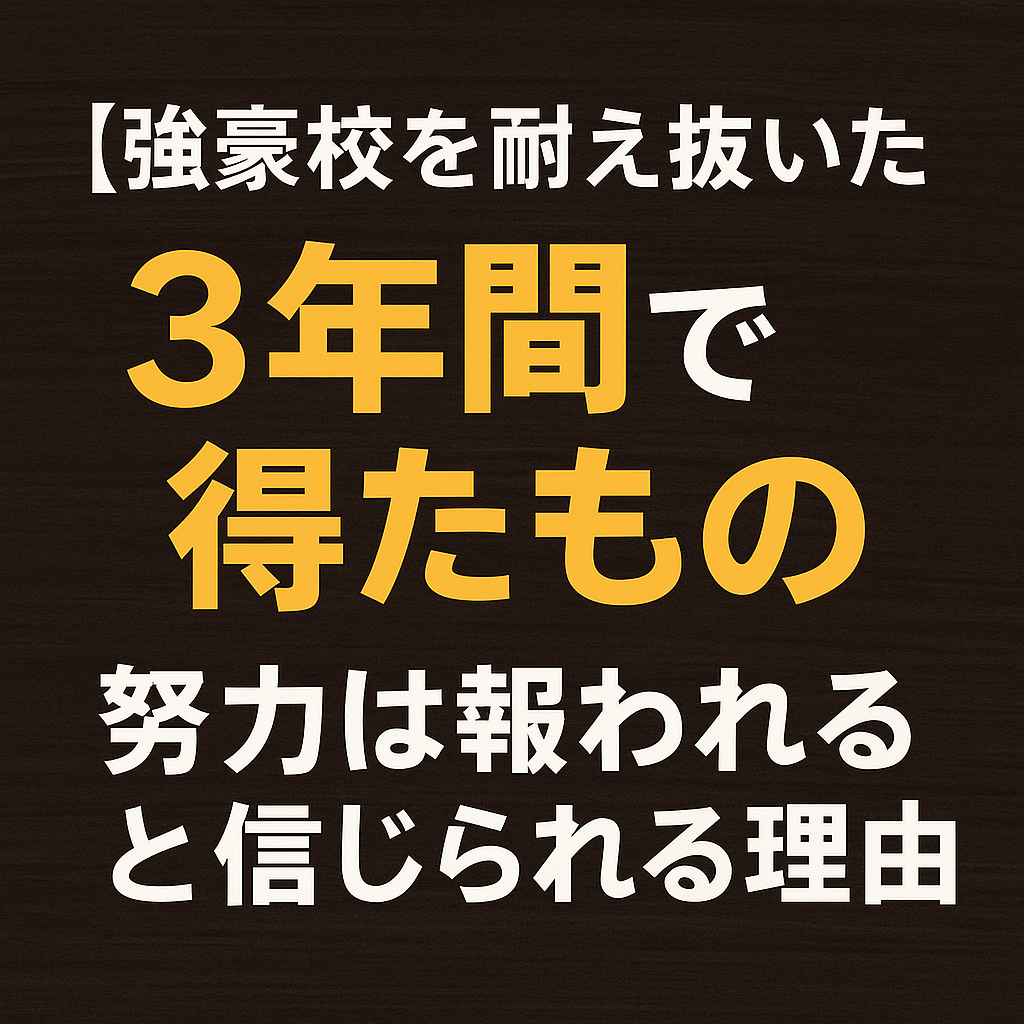「あの3年間は“努力”だったのか?それとも“耐え抜いた”だけだったのか?」
高校時代、私は全国大会常連のラグビー強豪校に所属していました。
毎朝の練習、夜は22時近くまでのトレーニング。
毎食1kgの米を食べ、試合に出られるかどうかもわからない状況で、先輩のしごきや理不尽に耐えながら過ごした3年間。
それでも、私はこの3年間を「耐え抜いた」と胸を張って言えます。
でも、ふと立ち止まって思うのです。
「あれは“努力”だったのか?」
■ 「耐える」ことに精一杯だった日々
練習は厳しく、毎日の生活はまるで軍隊のようでした。
1日の大半はラグビーに時間を奪われ、食事も睡眠も、すべてが「ラグビーのため」。
気づけば、自分で考える余裕なんてなかった。監督におびえ、先輩に言われたことをこなす、それだけで精一杯。
正直、燃え尽きました。
高校を卒業してからもラグビーは続けましたが、心のどこかで「もういいや」と思っていたのかもしれません。
大学ラグビーは、惰性でやっているような日々。体は動いても、心がついてこない。あれだけ全力でやっていたはずなのに、不思議と虚しさだけが残っていました。
■ 「努力」していたのは、あの男だった
そんな中、私とは違う姿勢でラグビーに向き合っていた仲間がいました。
彼は、決して上手な選手ではありませんでした。
けれど、練習が終わったあとも1人でボールを握り、監督に「帰れ」と言われるまで居残りしているような選手でした。
上手くなるスピードは決して早くはない、むしろ遅いから意味ないだろうと思っていました。
でも確実に、少しずつ少しずつ前に進んでいた。
大学卒業後、彼は実業団チームに進みました。
私はその知らせを聞いたとき、心の底から「やっぱりな、、」と思いました。
すごいではなく「やっぱり」なんですね、それくらいの努力を見てきたので、かえって当然のように思えました。
それと同時に、自分との違いをはっきりと感じたのです。
「彼は“耐えた”んじゃない。“努力”していたんだ」と。
■ 副キャプテンになって気づいた“リーダーの努力”
私はチーム事情もあり、3年生の途中から副キャプテンを任されました。
最初は「チームを引っ張らなければ」と、強い口調で周囲を動かそうとしていました。
でも、全然うまくいかなかった。
人は命令だけでは動かない。
誰も、ついてきてはくれませんでした。
やがて気づいたのです。
「自分が行動で示さなければ、誰も動かない」と。
そこからは、「引っ張る」のではなく、「常に先頭を切る」ことを意識するようになりました。
そうすると、不思議とチームが一つの方向に向かっていくように変わっていきました。
リーダーとしても、プレイヤーとしても、やはり“能動的な努力”が大事なのだと知りました。
■ 「強豪校で過ごす意味」は結果だけじゃない
強豪校の部活と聞くと、「試合に出られなければ意味がない」「練習が厳しすぎて潰れてしまう」と感じる人もいるかもしれません。
でも、私はあの3年間に意味があったと思っています。
たとえ試合に出られなかったとしても、「自分と向き合った時間」が確かに存在していたからです。
そして何より、そこには「本気で自分を磨こうとする人たち」がいた。
もし高校時代だけを見てしまうと、試合に出られた・出られなかった、活躍できた・活躍できなかった。そこだけを見てしまいますよね。
だけど、その3年間で見た景色は必ずどんな形でも自身の成長を後押ししてくれる”経験”として生き続けます。
■ 最後に|今、挑戦を迷っている君へ
あなたがもし、強豪校に行こうか迷っているなら。
厳しい部活に挑むべきか悩んでいるなら。
私はこう言いたい。
「一度、挑戦してみてほしい」
3年間、ただ“耐え抜く”だけでは意味がない。
でも、“自分の意思で努力”すれば、きっとその時間は自分の財産になります。
苦しさの中で見える景色、仲間との絆、自分自身への信頼――
それは、机の上では学べない大切な経験です。
あなたは「耐えている」だけですか?
それとも「努力」していますか?